《追悼寄稿》大林宣彦監督は、「ずっと正しい少年だった」

1992年『おおさか映画祭』にて、大林宣彦監督(左)と春岡勇二
数々の名作を残し、大林宣彦監督が2020年4月10日にこの世を去った。最後の作品『海辺の映画館-キネマの玉手箱』が、新型コロナウイルスの影響さえなければ公開されていたはずの日だった。生前からインタビューなどで交流し、40年以上も彼の作品を観続けたファンでもある、映画評論家の春岡勇二が監督との記憶と想いを執筆する。
「松竹の試写室で心がぐちゃぐちゃになった」
「『さ』という字が、『び』という字をおんぶして、しんぼうしんぼう、さびしんぼう」(1985年『さびしんぼう』より)。
大林監督作品のなかでなにが好きか、なんて選べない。『転校生』(1982年)はいつ観たって新鮮だし、『時をかける少女』(1983年)の原田知世は圧倒的にかわいい。
2019年、雑誌「キネマ旬報」が同誌の創刊100年特別企画としておこなった、10年ごとのベスト・テンを決める「1990年代日本映画ベスト・テン」で、コメントを書かせてもらった『青春デンデケデケデケ』(1992年)には特別な思い入れがある。不良でもなんでもない、むしろ優等生的な少年たちがロックに目覚めバンドを結成する。そのストーリーの奥に在る、少年たちの普遍的で尊い情熱の核が、時代を越え、ロックや映画といった対象も越え、まさにデンデケデケデケと胸に響いたのだ。それはむしろ、現役の少年よりも、かつてのロック少年、映画少年の胸にこそ強く鳴っただろう。友人の初恋のために、三田明の『美しい十代』を演奏する少年たちは素敵だった。

遡ると大学1年のとき、映研の先輩たちが「ハウス」「ハウス」と騒いでいた。大林監督の商業映画デビュー作『HOUSE ハウス』(1977年)のことなのはわかっていた。すぐに天王寺の「あべのアポロシネマ」に観に行った。『家』に喰べられてしまう美少女たちを描くファンタジー・ホラー。『おしゃれ』『ファンタ』なんていう少女たちの呼び名も気恥ずかしく、挿入されるアニメやチープな特撮にも「なんだこれ」と思いつつ、心奪われた。しばらくの間、人に「『HOUSE』どうだった?」と訊かれると、「変な映画、でも面白いよ」と答えていたのを40年以上経ったいまも覚えている。
1989年、松竹の試写室で心がぐちゃぐちゃになった。あんな経験は後にも先にもない。スクリーンに映されていたのは『北京的西瓜(ぺきんのすいか)』の37秒の空白。撮影予定の直前に起こった天安門事件によって、中国ロケが中止になったことをそれは伝える。怒りか、悲しみか。間違いなくあるのは、ロケができなかったために画がないという事実。それをこういう形で残し、伝えた監督の誠実さに震えた。
『海辺の映画館-キネマの玉手箱』
近日公開
監督:大林宣彦
出演:厚木拓郎、細山田隆人、細田善彦、吉田 玲、成海璃子、山崎紘菜、常盤貴子
製作:『海辺の映画館-キネマの玉手箱』製作委員会
配給:アスミック・エース
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
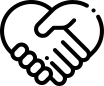 コラボPR
コラボPR
-

【大阪・関西万博2025】最新情報まとめ!地元編集部が取材してわかった、人気グルメから穴場スポットまで
NEW 23時間前 -

大阪のおすすめビアガーデン2025年最新版
NEW 2025.7.8 12:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫
NEW 2025.7.8 11:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版
2025.7.3 12:00 -

まさに旬!大阪難波のホテルで白桃アフタヌーンティー[PR]
2025.7.1 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年下半期の運勢は?
2025.7.1 00:00 -

神戸のおすすめビアガーデン2025年最新版
2025.6.30 11:00 -

「街ナカ」ホテルスタッフ、OMOレンジャーを直撃![PR]
2025.6.28 10:00 -

京都駅から約16分で行ける!宇治で5時間鬼スケ旅[PR]
2025.6.27 07:00 -

大阪土産で会話も弾む!ガンダム、限定味…駅近の最新菓子[PR]
2025.6.20 07:00 -

京都・貴船&高雄のおすすめ川床、ランチからカフェまで【2025年】
2025.6.19 12:00 -

万博から30分…大阪の駅近ホテル、快適すぎた[PR]
2025.6.12 07:00 -

京都・川床おすすめランチ&ディナー、鴨川・貴船・高雄エリア別【2025年】
2025.6.11 15:00 -

奈良のおすすめビアガーデン2025年最新版
2025.6.6 16:30 -

京都・滋賀のおすすめビアガーデン2025年最新版
2025.6.5 11:00 -

神戸のホテルで贅沢に、アフタヌーンティー2025年最新版
2025.6.4 11:00 -

京都のホテルで楽しむ、アフタヌーンティー2025年最新版
2025.6.3 12:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.4.10 11:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版
2025.4.2 19:30 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】
2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版
2025.3.31 16:45



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア









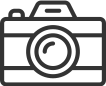 写真ランキング
写真ランキング













 ピックアップ
ピックアップ







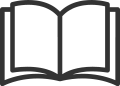 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

