三池監督、玉砕の先にある映画の可能性

さだまさしが1987年に発表した「風に立つライオン」。その楽曲に惚れ込んだ大沢たかおが、小説化と映画化を熱望し、自らプロジェクトを立ち上げた同名映画がいよいよ完成した。メガホンをとったのは、バイオレンス映画といえば・・・の三池崇史監督。先だって行われた記者会見では、「よくある”泣けたことを喜ぶ映画”にはできないな」と語った監督だったが、その映画『風に立つライオン』の製作について、評論家・ミルクマン斉藤が直撃した。
取材・文/ミルクマン斉藤 写真/本郷淳三
「感情は揺れても、できるだけ涙はこらえてもらいたい」(三池崇史)
──監督のフィルモグラフィは本当に膨大で、でもVシネマも含めてほぼ観させていただいているんですけれど、今回はやはりその中でもかなり異色であることは否めない気がします。
映画が、というか登場人物がそういう人間なんで、これをそんなに暴力的に変えてしまうってことはできなかったんですね。逆に、自分が今まで出会ったことのない(タイプの)島田航一郎という人間が、我々のやったことのないところに連れて行ってくれる、それが自分にとってこの映画を撮るという作業だと思ったんです。
──いや、俗に三池監督はヴァイオレンスの監督だと言われますけれど、決してそういうもので括れる監督ではないと思っているので、こういう堂々たる、公明正大な映画を撮られたとしても実は全然不思議でもなんでもないんですけれどね、いち三池ファンとしては。しかも昨年の12月に撮了されて、たった3カ月後の公開でこのスケール感とクオリティという。でも海外ロケで、これだけ大がかりな撮影を敢行されたのは、おそらく『中国の鳥人』(1998年)以来じゃないですか?
そうですね。『中国の鳥人』のときはロー・バジェットであれをやって。まずプロデューサーをクルーから外して、(中国の奥地へ)旅をして、「こうやればこうなる」って(予定調和をなくす)チャレンジだったんです。作り方そのものを変えていかないとできない作品というのにたまに出合うんですが、これもケニアに行った人の話をケニアで撮ろうと試みないというのはまず作る権利がないな、と。主人公の島田航一郎に申し訳ない、というか、彼を描く土俵にそもそも立てもしないな、という気がしたので。

──やはりあちらへ赴いて撮るというのは、日本映画として前例もないし、いろいろと大変ですよね。
プロデューサーは嫌がりますよね、よく判らない土地だし、リスキーだし。でも、そのリスクにこそ本当は映画の、全部じゃないけどひとつの魅力があるのは確かなんですよね。みんなで注射を打ってねぇ。予防接種代だけで2,000万円近い(苦笑)。
──え~!そうなんですか? スタッフ全部合わせるとそんなになるんだ。
安くしてもらっても、ひとり1万数千円かかる。そういう注射代の交渉もしましたねぇ。でもエンタテインメントの根っこにあるのは、やっぱり玉砕覚悟で突っこんでいく奴らがいるか、ということだと思うんです。そいつらの作った作品が失敗作であろうが、その失敗が心地良いというか。そこに可能性を感じるんですよね。今はどうしても、やりやすい環境の中で映画を処理しようとする。ヒーローものにしても、バイクで転ぶと危ないから車に乗ったりとか、そういう風にリスクを避ける風潮なんですね。それはやっぱりいかがなものか、と。ビジネスをやってる人なら、未開発のところに飛びこんでいったり、自分のノウハウを活用して常識を壊していくのは当たり前なんだけど、映画の人間が今、それができなくなってきている。この作品はそれを「やれ」と言ってるんだなと。実は映画にとって重要なところじゃないかと思います。
──まさにこの映画には、ケニアに行かなければ得られないランドスケープがいっぱいありますね。三池監督の作品って、広くて荒涼とした空間の中に人間がぽつねんと立つ、というハードボイルドといってもいい構図が多いと思うんですけれども、今回はケニアのシーンにしても日本のシーンにしても、そうした大きな風景の中に人間が1人立つ、まさに「風に立つライオン」的なショットが多いように感じましたが。
そうですよね。仲間や友人がいて、その中で自分の立ち位置というか、生きていきやすい環境をなんとか作ろうとするのだけど、結局は自分自身との戦いが常にあって、それはもう孤独なわけですよ。その孤独感っていうのはエネルギーとして絶対必要なのに、なんか今、我々は誤魔化してる。忘れつつある。横できちんと繋がっていけるっていう、そういう匂いがどうも胡散臭くなってきて。

──「絆」なんて言葉がちょっと安易に使われ過ぎた感もある3・11が、物語の枠にもなっていますしね。
この映画が素晴らしいなと思うところは、登場人物が自分と戦っているところですね。(彼らの)人生は全部縦だけなんですよ。仕事上ぶつかったり仲間になったりもするけど、自分の道はまっすぐ前を向いていく。友情の尊さよりもっと大切なことがあるっていうのを、僕は原作を読んで感じて、泣けてくるわけですよね。それが同情とか悲しみじゃなくて、気持ちのいい涙なんですよ。ただ映画としては、思いっきり泣ける編集にして、泣ける音楽で、っていうのもできるんですけれども、感情は揺れてもできるだけ涙はこらえてもらいたいなぁ、と。今は「泣く」という行為で得たものを吐き出す、というか全部発散しちゃう感じがして、泣くことで完結するというか、逃がしてしまうような気がして。だから、どちらかというと淡々と描いていって「ここで泣いてください」「ハイ、ここですよ」というのはあまり明確にはしない作品にしたつもりなんですけど。
──確かに、周到なまでに泣きの要素は避けてられるな、と。まぁ僕は、人間というものはすべからく「さだまさし好き」と「さだまさし嫌い」に分かれると思うんですけれども(笑)、それは「さださんの歌は泣けて仕方がない」「いや、絶対にこれでは泣きたくない」の二派がある、というか。この映画の監督が三池監督だと聞いたときはもう「意外すぎる」の一言に尽きましたから(笑)。
さださんも「え~!」って言ったでしょうね。「なんで?」って(笑)。
──そこがやっぱり面白いところで、縦の線で生きていた人間が違う場所での経験を積むことによって横の線ができるっていうのは、まさに三池映画っぽいなと思ったんですよ、構図としては。三池監督のある種ハードボイルドな人間の描き方みたいなものにも通じるな、と。
航一郎がね、幸いにも偉そうなことを言うわけでないんで。ケニアの少年に対しては精一杯、本音で正直に語ってるんでしょうけど、こういう風に生きろと強要するわけでもないし、むしろ愚かさも含めて見せていくんですよ。不器用なというか、そう判断するか?というか、その辺がすごく好きなんですよね。
──その愚かさとか、ちょっと常軌を逸したところのある判断っていうのは、航一郎はなんだか自分から、死に向かって進んで行ってるんじゃないか、って感じがとてもするんですよ。
撮り始めてしばらくして、中盤過ぎた辺りで大沢さんが「島田航一郎って本当に人として存在したんですかねぇ?」って言ったんです。映画の流れをそういう目で見ると、航一郎はケニアにひとりだけ、3日間遅れて来るんですよね。街の中から子供たちに紛れてふわ~っと現れて、いろいろ経験して、いろんな人たちに会って。で、過去を遡っていくと、長崎でいろんなことがあると。で、誰も知らない場所でフッと消えていく。消えていくっていうのは、おそらく死んだんだろうと。それを演じてる大沢さんが感じてるわけで。それは面白いなぁと。その存在があってこそ初めて、フィクションであるこの人物が映画の中でリアルに見えるんじゃないかな、って。映画に存在すれば現実に存在するのと同じ価値を持つ、とはなんとなく予感はしたんですよね。ドキュメンタリーだけがリアルに何かを描き出すわけじゃ決してないんですよ。
──そうなんですよね。映画を観ているときは実話ベースだと思いましたが。実は島田航一郎というのはフィクションであって、モデルの方はまだご存命だというのを後で知って。ま、それでどうこう、ってことはないのですが。
そうです。長崎大学からケニアに行かれて・・・そのあたりは同じなんですよ。モデルは柴田紘一郎先生というんですが、その先生とさださんのお父さんが友人で。さださんが20歳の頃に酒の席に同席していて、その人が話すケニアの話や自然の話、研究している吸血幼虫とかワケのわからない寄生虫とか、向こうの風土病とかの話に、頭がいっぱいになったという。それから十数年経って、発酵して、自然と「風に立つライオン」っていうタイトルになって現れてきたわけですよ。
映画『風に立つライオン』
2015年3月14日(土)公開
原作:さだまさし(「風に立つライオン」幻冬舎文庫)
監督:三池崇史
出演:大沢たかお、石原さとみ、真木よう子、ほか
配給:東宝
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
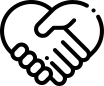 コラボPR
コラボPR
-

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2024年最新版
NEW 2024.4.17 14:00 -

ホテルで甘いものを満喫、関西スイーツブッフェ・リスト
NEW 2024.4.17 14:00 -

新しくなった西宮ガーデンズで新店巡り[PR]
2024.4.12 11:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2024年最新版
2024.4.4 12:00 -

鉄道系YouTuber西園寺、フリーきっぷで高知旅[PR]
2024.3.29 13:00 -

さらに便利に!子ども連れに人気のガーデンズ[PR]
2024.3.29 07:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごブッフェまとめ・2024年版
2024.3.26 13:00 -

「これハマる」女子が喜ぶスポーツ観戦とは?[PR]
2024.3.26 12:00 -

高知の観光&おでかけ&グルメ情報、2024年最新版[PR]
2024.3.23 09:00 -

家族で遊べる「まきのさんの道の駅・佐川」の遊び方[PR]
2024.3.23 09:00 -

知る・買う・食べる!牧野植物園「ラボテラス」[PR]
2024.3.22 09:00 -

関西で楽しむ春のお花見、桜の名所
2024.3.21 11:00 -

体験・温泉も、泊まれる伝統工芸の里がアップデート[PR]
2024.3.21 09:00 -

高知が誇る絶景温泉と藁焼きカツオに浸れる名湯宿[PR]
2024.3.20 09:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごブッフェまとめ・2024年版
2024.3.19 14:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごブッフェまとめ・2024年版
2024.3.19 13:00 -

噂のあの店も! 阪急西宮ガーデンズがリニューアル[PR]
2024.3.14 07:00 -

【大阪編】今買いたい、手土産まとめ
2023.11.20 15:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア















 ピックアップ
ピックアップ










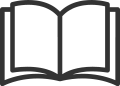 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

