日本のポップ・マエストロ、高野寛に訊く新バンドと今の音楽環境

1988年のデビュー以来、ソロとしての活動のほかに、BIKKE、斉藤哲也とのNathalie Wiseや宮沢和史(THE BOOM)とのGANGA ZUMBA、高橋幸宏、原田知世とのpupaなど、数々のバンドも並行に行ってきた高野寛。
ミュージシャン、プレイヤー、プロデューサー、そして日本のポップ・マエストロとして、その才能を遺憾なく発揮してきた彼が、2012年に新たにスタートさせたのが、クラムボン・伊藤大助との2人組バンドだ。プライベートセッションをきっかけに生まれたこのバンドは、デビュー24年を迎える高野寛にとっていったいどういうものなのか。取り巻く音楽環境と共に話を訊いた。
写真/木村正史
「自己プロデュース能力が問われている時代」(高野寛)
──新たなプロジェクト「高野寛+伊藤大助」のライブアルバム『TKN+DSK LIVE 2012』が10月31日に出たわけですが、そのお話をうかがうにあたり、少し遡ってお聞きできればと思ってます。
はい。
──高野さんがシングル『See You Again』でメジャーデビューしたのが、1988年。その当時、すごくシンガーソングライター色が強かったんですけど、その頃と今を比べて音楽的なスタンスに違いとかありますか?
基本的には変わってないと思うんだけど、デビュー当時はやりたいことに近づくためにはどうすればいいか、それを四六時中考えてましたね。いつも理想がずっと遠くにあって、手が届かないもどかしさがあって。それはソングライティングもそうだし、ライブのプレイもそうだし。ずっとそういう想いはありましたね。
──デビューした頃は、理想の方が遠くにあったとおっしゃられてましたけど、今はどうですか? 理想に追いつくように・・・。
いやぁ、まだまだやれないこともあるんだけど、想いを形にするスピードはすごく早くなりましたね。だから、今回みたいにリリースしてない音源を、たった1回のツアーをやっただけでライブ盤として発売するなんて、昔から考えれば夢の夢ですよね。
──いわゆる、音楽業界のシステム的な問題もありつつ。
そうそう。以前はがっちり決まっていたフォーマットもシステムも、今はすごく自由になりましたね。インターネットもあるから、発信したいという想いさえあれば、その後の道筋はいろんな方向に開かれていて。まぁ、裏を返せば、すごく自己プロデュース能力が問われている時代なんだけど、僕自身はそこに対応できるだけのいろんな経験をしてきた気がしますね。

──今言われた理想という部分なんですけども、20年以上も活動していくと、どこかで枯渇したり、挫折したりしませんでしたか?
う~ん、何回かありますよ。枯れてしまったときはね。そういうときは、人とやることでしか乗り越えられないと、実感として知っていて。たとえば、自分よりも年下のミュージシャンと一緒にやることでなにか新しい感覚をもらったりとか。あとは、バンド活動。2000年以降はいくつかバンド(※Nathalie Wise、pupa、GANGA ZUMBAのメンバーとしても活動中)をやってきたんですけど、そういうなかでソロとは違う作り方をしたり。
──意識的にそれをやってきた、バンドを選んできたところはあるんですか?
そうですねぇ。まぁ、違っている方が面白いし、自分をバージョンアップさせるためにバンドをやっているんで。むしろ違ってないと意味がないと。
──バンド活動しているときでも、高野さんのソロというのはひとつの基軸として常に持ち続けているんですか?
そうですね。曲を作るということは、僕の人生の一部なんです。締め切りがないと曲が作れないという人もいますが、僕はそうではなくて、常に作っている方が楽しいし、締め切りに追われず作る方が性に合っていて。だから、バンドをやっているときでも、このバンドには合わないけれど、自分が歌ったら面白いんじゃないかという曲ができるから、そういうのはいっぱいストックしてある。まぁ、締め切り直前に、火事場の馬鹿力で作ったシーンは何度もあるし、そこで気に入っている曲もいっぱいあるんですけど、まぁ、しんどいですよね(笑)。
──それをずっと20年以上も、デビューする前も含めてだと思うんですが、音楽の作り方、向き合い方というのはその時々で変化してくるものなんですか?
そうですね。言いたいことが見つからない時期というのも少なからずありましたね。特に歌詞は自分の気持ちとより繋がっている部分なので、歌いたいことが見つからないのは、シンガーソングライターとしては最大の危機ですよね。そういう時期も、正直ありました。そのときはバンドに助けられましたね。
──個人的な感想なんですが、2009年にシングル『Black&White』(亀田誠治プロデュース)が出たときに、初期の高野寛が帰ってきたような印象があったんですね。もちろん、ソロ作なので当然なんですけど、それ以前は、ややプレイヤー寄りな活動をされてた時期もあったので。
あれの前から徐々に始まってたんですけど、『Rainbow Magic』(2009年)というアルバムを作って、その最後に「虹の都へ」のセルフカバーを入れたんですね。タイトルに「Rainbow」という言葉を織り込むこともそうだし、ちょうどデビュー20周年で、この時期にしかできないことをやろうって気持ちが単純に強くなって。
さすがにこれだけ時が流れると、ヒット曲に対して持っている葛藤やこだわりもずいぶん無くなってきていて、しばらく歌っていない時期もあったので、むしろ新鮮な気持ちで昔の代表曲を歌えるような気分になってたんですね。
──『虹の都へ』『ベステンダンク』のヒットが予想以上という感じだったんですか?
そうですね。自分の作品がヒットして、街で指さされるような、いわゆるスターみたいな扱いをされる想定がまったくなかったので。相当面食らいましたね。アマチュア時代はハードロックとプログレと、テクノとニューウェーブが好きだった人間なので(笑)、そもそも自分が観に行くライブの客層も男子が8割だったんですよ。そういうフィルターを通してできたはずの曲が、なぜか自分がライブをやると9割以上が女子という。もう、どうしたらいいんだろう? って感じになりますよね(苦笑)。
──その20周年をやったことで、歌の捉え方みたいな部分に、変化はありましたか? もしくは気付いたこととか。
実は意図的に歌を変えていた時期があって、Nathalie Wiseをやり始めた頃は特にそうなんだけど、バンドのレコーディング初日にちょうど911の事件があって。みんなとスタジオで映像を見てたんですけど、それがすごいショックで。ものすごい心の傷になったんですね。
その頃はブラジル音楽にはまって、ボサノヴァの囁くような歌い方がいいなって思っていたんですけど、その911のショックがさらに内省的な方向に拍車を掛けて、盛り上がるとかシャウトする感覚を、そこから何年間か忘れてたくらいで。あんまり好きな言葉じゃないけど、自分を癒やすような気持ちで歌っていた部分がありますね。Nathalie Wiseの頃は特にそうでしたね。
──そうなると、今度はメッセージ性というか、なにを発信するか、なにを届けるという部分に焦点が当たってきますよね。
うん。だから、それで生まれたのが今回のライブ盤にも入っている『確かな光』という曲だったり。社会へのメッセージというよりは、心の叫びみたいな歌がいくつかありましたよね。とにかく不安な気持ちが強かったですよね。で、実はね、今回のアルバムに入っている『いちぬけた』という曲も、この時期のものなんですよ。
不安とか焦燥感でできた曲がいくつかあったんですが、それがこの震災以降、違う形で自分のなかにバーンと浮かび上がってきて、そういえばあんな曲があったなと、ちょっとだけ歌詞を直して歌ったりしていて。インスパイアの源は全然違うところにあるんだけど、時代が変わったことで、僕のなかで断片的だった歴史が妙に繋がってきたりして。2001年以降の感覚ですね。
高野寛
高野寛(たかの・ひろし)
1964年生まれ、静岡県出身。大阪芸術大学卒業。1988年、シングル『See You Again』(高橋幸宏プロデュース)でデビュー。1990年リリースの『虹の都へ』『ベステンダンク』(共にトッド・ラングレンのプロデュース)が大ヒットを記録。また、Nathalie Wise、GANGA ZUMBA、pupaなど、バンドでの活動も精力的におこなっている。これまでにベスト、ライブ盤を含む16枚のアルバムをリリース。2012年1月にクラムボンのドラマー・伊藤大助との2人組バンド、高野寛+伊藤大助を結成した。
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
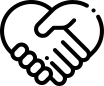 コラボPR
コラボPR
-

【大阪・関西万博2025】最新情報まとめ!地元編集部が取材してわかった、人気グルメから穴場スポットまで
NEW 10時間前 -

10万円の宿泊券も!大阪の商業施設で太っ腹企画[PR]
NEW 13時間前 -

大阪のおすすめビアガーデン2025年最新版
2025.7.8 12:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫
2025.7.8 11:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版
2025.7.3 12:00 -

まさに旬!大阪難波のホテルで白桃アフタヌーンティー[PR]
2025.7.1 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年下半期の運勢は?
2025.7.1 00:00 -

神戸のおすすめビアガーデン2025年最新版
2025.6.30 11:00 -

「街ナカ」ホテルスタッフ、OMOレンジャーを直撃![PR]
2025.6.28 10:00 -

京都駅から約16分で行ける!宇治で5時間鬼スケ旅[PR]
2025.6.27 07:00 -

大阪土産で会話も弾む!ガンダム、限定味…駅近の最新菓子[PR]
2025.6.20 07:00 -

京都・貴船&高雄のおすすめ川床、ランチからカフェまで【2025年】
2025.6.19 12:00 -

万博から30分…大阪の駅近ホテル、快適すぎた[PR]
2025.6.12 07:00 -

京都・川床おすすめランチ&ディナー、鴨川・貴船・高雄エリア別【2025年】
2025.6.11 15:00 -

奈良のおすすめビアガーデン2025年最新版
2025.6.6 16:30 -

京都・滋賀のおすすめビアガーデン2025年最新版
2025.6.5 11:00 -

神戸のホテルで贅沢に、アフタヌーンティー2025年最新版
2025.6.4 11:00 -

京都のホテルで楽しむ、アフタヌーンティー2025年最新版
2025.6.3 12:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.4.10 11:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版
2025.4.2 19:30 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】
2025.4.1 11:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア








 人気記事ランキング
人気記事ランキング




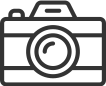 写真ランキング
写真ランキング













 ピックアップ
ピックアップ







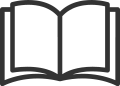 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

