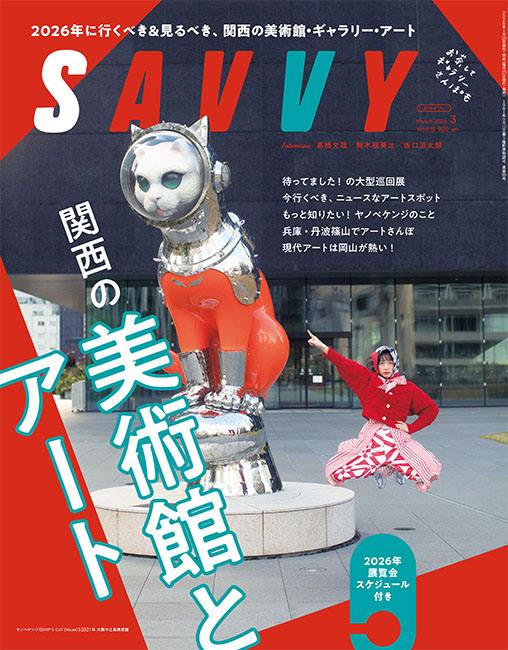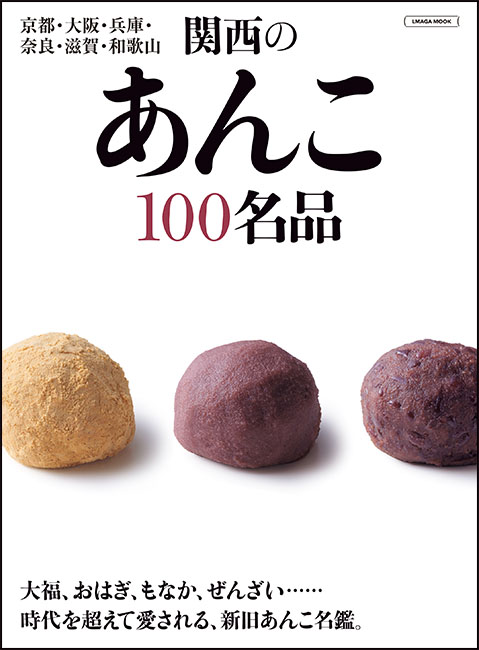暗殺者・佐野政言、歴史の偶然で「大明神」に【べらぼう】

『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第28回より。切腹を命じられる旗本・佐野政言(矢本悠馬)(C)NHK
横浜流星主演で、数多くの浮世絵や小説を世に送り出したメディア王・蔦屋重三郎の、波乱万丈の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK)。7月27日の第28回「佐野世直大明神」では、田沼意次の息子・意知が、佐野政言に襲撃されて落命。政言が当時の庶民から神のように祀り上げられた理由と、意次がこの悲劇をいかにバネにしたのかに注目してみた。
■ 暗殺者のはずが大明神に…第28回あらすじ
佐野政言(矢本悠馬)の刃に倒れた田沼意知(宮沢氷魚)は、父・意次(渡辺謙)に米の値段と蝦夷地の上知、そして身請けした誰袖(福原遥)の面倒を言い遺して死去。政言は切腹するが、その直後に生前の意知の政策によって、安価な米が市中に出回る。庶民はこれを佐野のおかげだと信じ込み「佐野世直大明神」と崇めるようになった。しかし重三郎は、一連の動きには裏で糸を引く人物がいると推察する。

重三郎に仇討ちをするよう進言された意次は、意知が死んだのは自分が父親だったせいだから、自分を討てと重三郎に言い放った。しかしその後重三郎に送った手紙には、意知の志を受け継ぎ、彼が生きていたら成し遂げたであろう政策を代わりに実現させることで、仇討ちをすると記していた。ちょうどその頃、蝦夷地を治める松前藩の不正の証拠を探していた平秩東作(木村了)が、ある帳面を命がけで持ち帰ってきた・・・。
■ なぜ、佐野政言は「庶民の神」になった?
あの『仮名手本忠臣蔵』の元ネタとなった、浅野内匠頭の「殿中でござる!」に次いで有名な、江戸城内で起きた刃傷沙汰となる、佐野政言の田沼意知暗殺事件。実際に政言は「覚えがあろう!」と言って意知に斬りかかり、意知はそれを刀の鞘で受けるものの、深手を追ってまもなく逝去する。

このとき意知が刀を抜かなかったのは、父と同じく武道が苦手だからではなく、当時江戸城には「刀を3寸(10cmぐらい)出したら改易」というルールがあったため、田沼家のためにそれを避けたのでは・・・と言われている。

そして本懐を遂げた政言は、意知が逝去した翌日に切腹を命じられる。このとき政言が手にしようとしたのが、刀ではなく木刀だったことを「?」と思う方もいただろう。切腹はこの時代になると、本当に腹を切ることはなく、木刀や扇を手に取った瞬間に介錯するのがお約束となっていた。倒れ込んだ政言の手がキレイなままだったのは、それが理由だ。ただ史実では、本物の刀を求めて駄々をこねたという話が伝わっているので、リアル政言さんは矢本版政言より、相当面倒か前時代的な性格だったのかもしれない。

そんな彼が、庶民から「大明神」として祀り上げられることになるのは、彼が死んだ頃から安い米が流通するようになったためだ。前回が2週間前だから忘れかけていたが、このとき意知は重三郎のアドバイスにのっとって、大量の米を幕府が買い上げて、安く市中に流すという政策に取り掛かっていた。
その効果が見事に働いたわけだけど、それがよりによって自分を殺した人間のおかげだと思われてしまうとは・・・。意知は非常に無念だろうが、この『べらぼう』の佐野なら「えー、どういうこと?」と、あの世で静かに戸惑いそうだなと想像する。
■ 一橋治済の誤算…田沼意次がパワーアップ
史実的には多分この事件とは無関係だと思われる一橋治済だけど、今回は仲良しの松前道廣(えなりかずき)を困らせるのが気に食わないという理由で、この一件を操るフィクサーとなった。そして意次ではなく意知をターゲットにしたのは、確かに意次を殺害すれば意知は発奮し、しかも父に負けないぐらい有能なので首尾よく蝦夷を召し上げたはず。しかし息子の方が死ねば、意次は気落ちして上知は断念、上手くいけば政界引退ぐらいに持ち込めると考えたのだろう。

しかし治済が誤算だったのは、重三郎が意次に仇討ちを提案したことをきっかけに、意次がむしろパワーアップしてしまったことだ。松前家との交友関係や、将軍家嫡男の死でもっとも利を得るのは誰かを考えたときに、どうやら一橋治済が源内の指摘した真の悪党だと推察した様子の意次。彼が弱りきったと油断して話しかけてきた治済に対して、体がなくなっても志は生きつづけるから、たとえ暗殺をしても無駄なことだと、見事な宣戦布告を突きつけることができた。

ここまでは笑顔で治済に語りながら、去り際に一転鋭い表情となって「やらなければならぬことが山のようにございます」=「蝦夷地の件はまだまだ進めるからな!」と告げるシーンでの、渡辺謙の表情の使い分けが、さすがハリウッドスターと感嘆する名演だった。そして重三郎が、平賀源内の志を未来へとつないでいくことを本屋のモチベーションとしているように、息子の志を実現していくことが、今後の意次の巻き返しの力となるのだろう。

もともと意次の身内を自分の家老にするぐらい、田沼家とは親しい間柄だった一橋治済だが、ここからしばらくすると意次を幕政から追い落とす側に回る。新しい勢力の方に分があると踏んだというのが一般的に考えられる理由だろうけど、その背景にこういう因縁話があったのだとしたら、治済が手のひらを返すのも当然と思われる。本当によくも毎回、残酷だけど理にかなったフィクションを重ね合わせてくるもの。この水面下での戦いの決着が、どのような形で着くのかも、今後の大きな見どころとなるのは確実だ。
◇
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合で毎週日曜・夜8時から、NHKBSは夕方6時から、BSP4Kでは昼12時15分からスタート。8月3日の第29回「江戸生蔦屋仇討(えどうまれつたやのあだうち)」では、重三郎が北尾政演(古川雄大)の持ち込んだ絵をヒントに、新しい黄表紙作りに取り掛かり、鶴屋喜右衛門(風間俊介)が意外な形でその話に乗ってくるところが描かれる。
文/吉永美和子
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
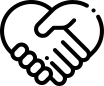 コラボPR
コラボPR
-

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]
NEW 8時間前 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題
NEW 2026.2.18 10:30 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版
NEW 2026.2.18 10:00 -

大河ドラマ『豊臣兄弟!』解説コラムまとめ【毎週更新】
2026.2.17 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.2.15 11:00 -

神戸のホテルでいちごスイーツ&自家製パン食べ放題![PR]
2026.2.15 10:00 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.2.13 11:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫
2026.2.5 11:00 -

「奥大和」ってどこ…?奈良で絶景アウトドア4番勝負[PR]
2026.2.4 17:00 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】
2026.2.3 12:00 -

人気!大阪でリンツチョコレートのアフタヌーンティー[PR]
2026.2.2 12:00 -

絶景なのに【穴場】…梅田・飲食フロアを網羅[PR]
2026.2.2 07:00 -

疑ってごめん、宮崎。「何でも極上」は本当だった![PR]
2026.1.31 08:00 -

神戸で極上いちごスイーツの祭典…人気シェフ夢の共演[PR]
2026.1.29 17:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.1.26 13:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.1.21 11:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.1.14 14:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ
2025.12.30 12:00 -
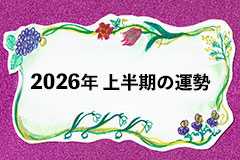
【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?
2025.12.26 00:00 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】
2025.12.20 19:00 -

【大阪・関西万博2025】半年間ありがとう!地元編集部が取材した人気グルメから穴場スポットまとめ
2025.10.13 11:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア






 人気記事ランキング
人気記事ランキング




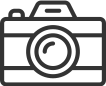 写真ランキング
写真ランキング





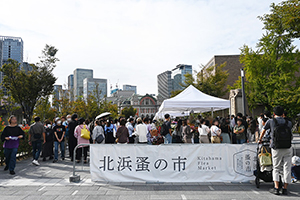




 ピックアップ
ピックアップ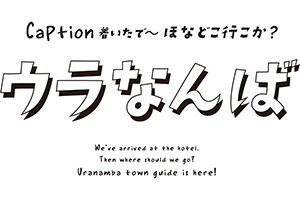

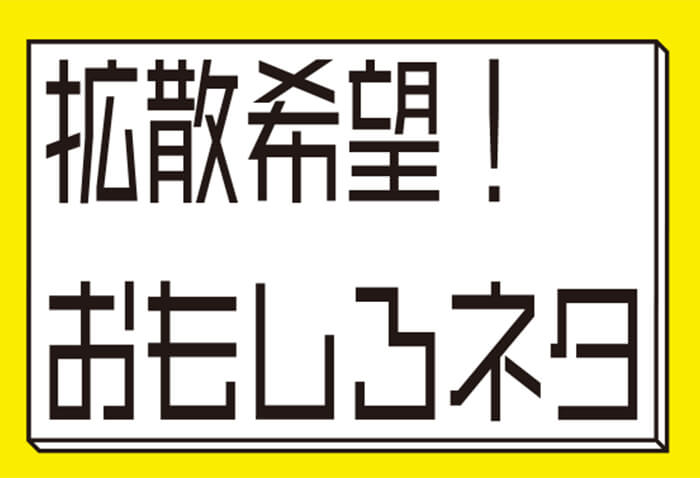


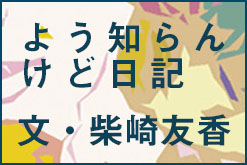

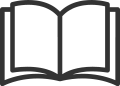 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本