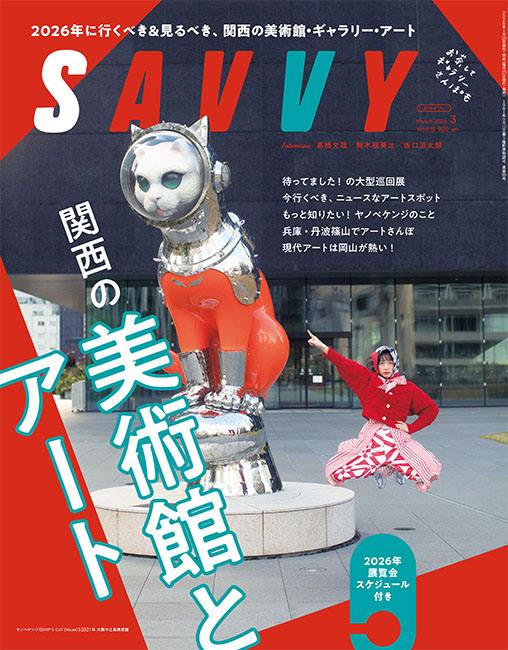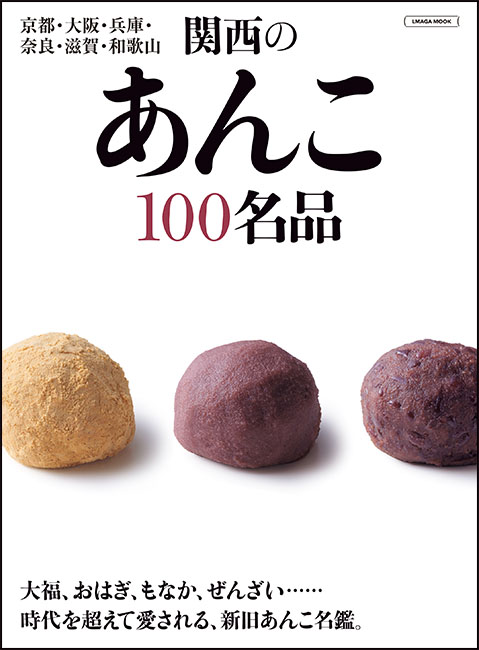本作りにも政治にもおよぶ、平賀源内の遺したもの【べらぼう】

『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第17回より。平賀源内の言葉を思い出す重三郎(横浜流星)(C)NHK
江戸時代のポップカルチャーを牽引した天才プロデューサー・蔦屋重三郎の劇的な人生を、横浜流星主演で描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK)。5月4日の第17回「乱れ咲き往来の桜」では、重三郎が「往来物」で新しい販路を作ったことと併せて、前回で退場した平賀源内のスピリットが、本作りの世界でも政治の世界でも、今もなお生きていることがうかがえる動きもあった。
■ 次期将軍探しが迷走、田沼は…第17回あらすじ
徳川家基(奥智哉)亡きあと、将軍・家治(眞島秀和)の後継探しが始まったが、御三卿の清水重好(落合モトキ)と一橋治済(生田斗真)はそろって辞退。さらに御三家にもふさわしい人材がいないという事態に、老中・田沼意次(渡辺謙)は当惑する。家治に今は亡き御台所と瓜二つの女性をあてがい、新たな男子の誕生を期待することにするが、それは家基の母・知保の方(高梨臨)の孤独を深めてしまうようになる。

この頃、意次が治める相良藩に新しい城が完成したので、意次は視察のために赴く。平賀源内(安田顕)の「まずは民が富む仕掛けを作る」という助言に従って町作りを行った相楽は、産業や商売が栄える豊かな地となっていた。意次はこの治世が日本国全体に行き渡るよう、幕閣の刷新を決意。嫡男・意知(宮沢氷魚)は、田沼家の格を上げるという家系図を持ってきた佐野政言(矢本悠馬)を、そこに加えるよう父に進言した・・・。
■ 定番だった「往来物」を、蔦重らしい新商品に
細見(ガイド本)、錦絵(グラビア本)、富本正本(公演パンフレット兼スコア)、青本(青年向け小説か漫画)と、回を追うごとに出版ジャンルをどんどん広げていっている重三郎。第17回では新たに「往来物」を手掛けることになった。ドラマのなかでも解説があった通り、手紙の往復書簡(往来)の形で読み書きを教える教材のようなもの。しかも商人や百姓、子ども向けから女性向けまで、年齢や職業に応じてさまざまな往来物が存在していた。

そういえば、紫式部(まひろ)が主役だった、前回の大河ドラマ『光る君へ』では、庶民の識字率が0%では? という平安時代の状況が明らかになっていた。それが江戸時代になると、多くの往来物が出版されたことで、庶民が積極的に文字を学ぶようになり、識字率は飛躍的に向上する。庶民に字を教えることへの理解を、周囲からまったく得られなかったまひろが知ったら、大いに喜んだのではないだろうか。
しかしこの往来物を出すにしても、重三郎らしい新機軸が、実に二重三重に仕掛けられていた。まず本の内容に関して、吉原に出入りする経験豊かな庄屋や商人、習い物の師匠など、各ジャンルのベテランにヒアリングを実行。そうするとやはり「この情報は古い」「役に立たない」など、現場の人間ならではの有益なアドバイスがバンバン出てきて、文字を学ぶ+αの情報の質が飛躍的にアップしたはず。

そしてこのヒアリング、重三郎が初めて吉原の細見作りに関わった際、現場の人間だからこその最新・正確な情報を盛り込むことができた、あの経験を活かしたからかな? と思っていたら、彼らを監修や共作者扱いにすることで、周囲に「これは自分の作った本だ」と宣伝してもらえるだけでなく、かなりの冊数を買い上げてもらうことを見越していたのだった。本当に何回も言うようだけど、本を作る能力と本を売る能力が、どちらも人並み外れているというのは尋常なことではない。
■ 平賀源内が遺した精神が、蔦重と田沼意次へ…
さらにこのアドバイスを求めたのが、江戸の人間ではなく地方の人間だったというのも、重三郎の抜かりなさだろう。江戸の人を使っても江戸の市中にしか広まらないが、地方の有力者を使えば、彼らのネットワークでおのずと広範囲に本が行き渡る。しかもほかの本屋がまったく目をつけてなかったルートだから、今後も販路を独占できる可能性が高い。「江戸で商売できないなら、地方で売ればいいじゃない」とは、まさに逆転の発想と言える。

そしてこのことは、平賀源内が重三郎に託した「本によって日の本を豊かにする」という言葉の意味を、改めて噛みしめることになった。自分の作る本が、江戸だけでなく「日の本」のすべての国を豊かにできるかもしれないということを、重三郎はこのとき意識したのではないだろうか。さらにそのきっかけを作ったのが、源内と共に行動してきた小田新之助(井之脇海)だったというのも、思いがけない所からパーツがハマったような感覚になった。
そして重三郎だけでなく田沼意次にも、平賀源内が遺したものの大きさを改めて知る機会があった。源内の助言ではじめた産業や道路の整備が、自分の領地を活気あふれる土地に変え、漁師たちがカツオを上納する(登場の仕方が直訴の勢いだったのが笑った)ほど、地元の人たちを喜ばせたのだ。この状況をもう少し早く知っていたら、源内先生も闇落ちせずに済んだのではないか。意次が密かに源内を助け出し、相良で隠棲させたという伝説が残っているそうだけど、『べらぼう』もそのルートを選んでくれたらよかったのに・・・。

前回であまりにも悲惨な退場をしてしまった源内だけど、その知恵と志は重三郎と意次という、出版・政治の各分野のパイオニアと成り得る人間たちに、しっかり受け継がれたことを実感できる回となった。重三郎はここからメディア王になる道をガンガン切り開いていくことになるが、「日本総相良計画」を進めようとする意次は、あまりにも今の幕府が伏魔殿すぎて相当な波乱が予想される。そして今回SNSが一斉に「息子の言うこと聞いて!」とシャウトしたその意味を、遠からず思い知ることになるだろう・・・。
◇
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合で毎週日曜・夜8時から、NHKBSは夕方6時から、BSP4Kでは昼12時15分からスタート。5月11日の第18回「歌麿よ、見徳(みるがとく)は一炊夢(いっすいのゆめ)」では、重三郎が捨吉と名乗る青年(染谷将太)と出会うところと、朋誠堂喜三二(尾美としのり)に思わぬ事態がふりかかるところが描かれる。
文/吉永美和子
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
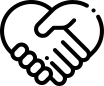 コラボPR
コラボPR
-

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]
NEW 2026.2.20 10:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題
2026.2.18 10:30 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.2.18 10:00 -

大河ドラマ『豊臣兄弟!』解説コラムまとめ【毎週更新】
2026.2.17 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.2.15 11:00 -

神戸のホテルでいちごスイーツ&自家製パン食べ放題![PR]
2026.2.15 10:00 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.2.13 11:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫
2026.2.5 11:00 -

「奥大和」ってどこ…?奈良で絶景アウトドア4番勝負[PR]
2026.2.4 17:00 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】
2026.2.3 12:00 -

人気!大阪でリンツチョコレートのアフタヌーンティー[PR]
2026.2.2 12:00 -

絶景なのに【穴場】…梅田・飲食フロアを網羅[PR]
2026.2.2 07:00 -

疑ってごめん、宮崎。「何でも極上」は本当だった![PR]
2026.1.31 08:00 -

神戸で極上いちごスイーツの祭典…人気シェフ夢の共演[PR]
2026.1.29 17:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.1.26 13:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.1.21 11:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.1.14 14:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ
2025.12.30 12:00 -
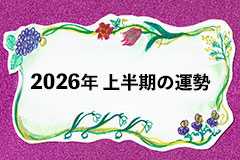
【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?
2025.12.26 00:00 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】
2025.12.20 19:00 -

【大阪・関西万博2025】半年間ありがとう!地元編集部が取材した人気グルメから穴場スポットまとめ
2025.10.13 11:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア






 人気記事ランキング
人気記事ランキング




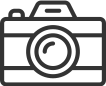 写真ランキング
写真ランキング











 ピックアップ
ピックアップ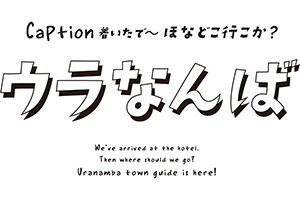

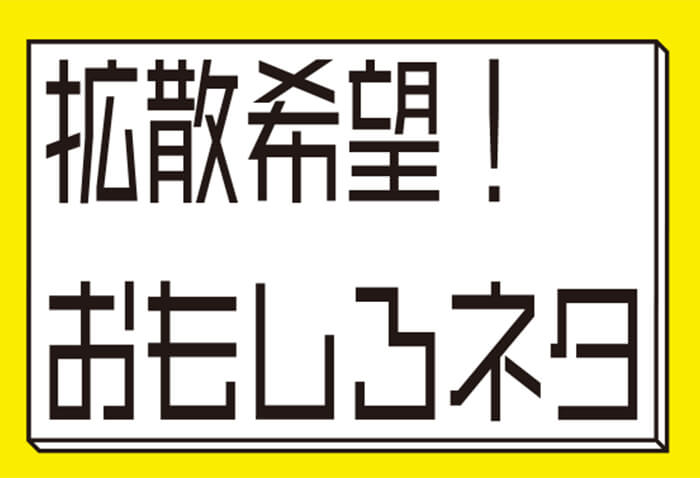


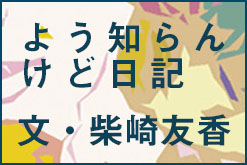

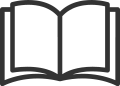 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本