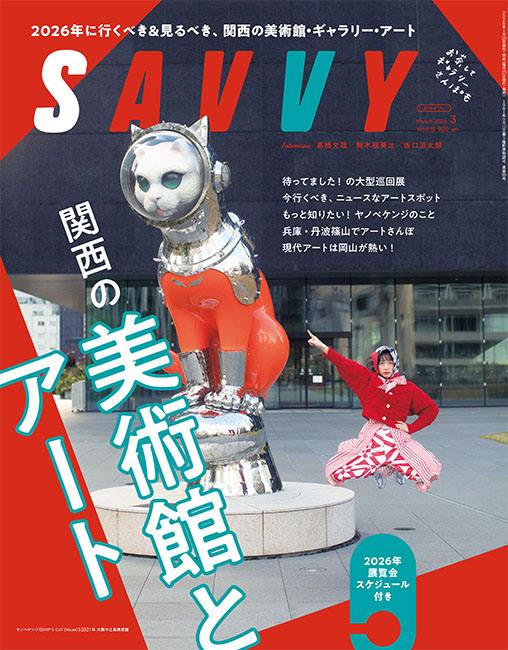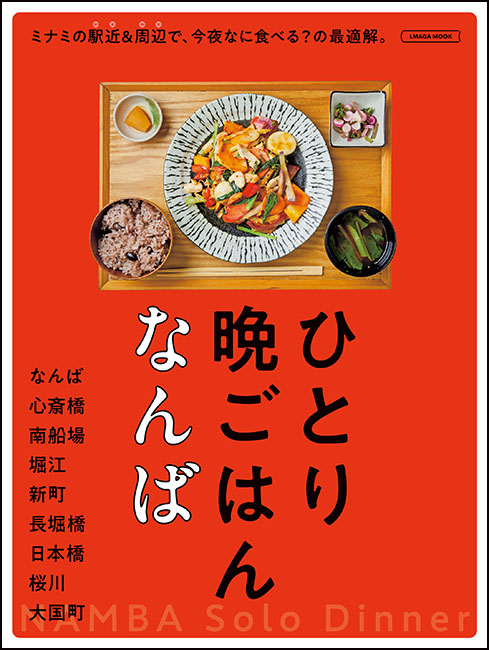「偏るという想定も」…前代未聞のお笑い賞レース「漫才×コント」、放送の反響は? 演出に聞いた

『ダブルインパクト~漫才&コント 二刀流No.1決定戦~2025』初代王者のニッポンの社長(c)日本テレビ・読売テレビ
今や毎月のように、全国のどこかでお笑いの賞レースがおこなわれているこの時代。2025年7月には、漫才とコントの二刀流王者を決める新たな賞レース『ダブルインパクト~漫才&コント 二刀流No.1決定戦~2025』(日本テレビ系)が初開催された。この演出を担当したのが、読売テレビ(ytv)の番組でプロデューサーなどをつとめている中屋敷亮氏だ。
大阪の若手芸人の登竜門的賞レース『ytv漫才新人賞』や関連番組『漫才Lovers』の演出も担当する中屋敷氏は、お笑い賞レースが多数誕生する今の流れをどのように見ているのか。そしてどんな意識で賞レースを制作しているのだろうか。(取材・文/田辺ユウキ)
■ お笑いファンが望む「新しい魅力」を模索した日々

──第1回『ダブルインパクト』にはどういった制作背景があったのか、あらためて教えていただけますか。
お笑いの賞レースがたくさんあるなかで、「この賞だけの要素はなんなのか」を考えました。ただ、お笑いファンが望んでないことをやってはいけない。その上で、新しい魅力について模索しました。特に難しかったのが、漫才とコントのどちらもやれて、どちらもおもしろいということのすごさの伝え方です。
──お笑いファンはそのすごさは分かりますが、お笑いをライトに見ている人は「なにがすごいの?」「どっちもできて当たり前じゃないの?」となりそうですね。
いろんな芸人さんに話を聞くと、やっぱり「両方できる芸人は憧れの存在だ」と。漫才、コントの両方がおもしろいというのは芸人として圧倒的に強いんですよね。『ダブルインパクト』の企画が立ち上がったとき、「どういう風にこの大会のことを説明しようか」と変換の仕方を議論したのですが、「最強の芸人とは?」のような方向に持っていけたらとなりました。芸人さんの底力や強さを打ち出せたらいいなって。

──煽りVTRのなかでセルライトスパの大須賀さんが、漫才師でもコント師でもなく「お笑い師になりたい」とおっしゃっていましたが、これが『ダブルインパクト』のキーワードになりましたね。
実力がないと、漫才、コントの2本で結果を残すことができない。第1回大会を見て、あらためて両方おもしろい芸人さんのパワーのとてつもなさを実感できました。
■ 「偏るという想定もしていた」…第1回大会を経て思うこと
──一方で課題として挙げられたのが、決勝7組中6組が1本目にコントを選択し、2本目に漫才をもってくるという「偏り」が出た点。この部分については『ダブルインパクト』独自の機能性が十分発揮されなかったように思えます。
当然、どちらかに偏るという想定もしていました。決勝戦ではみなさん「1本目で結果を出さないと、2本目はハードルが上がる」と考えていたはず。そこで自信があるネタ、もしくは印象に残るネタをやるという戦略があり、それが「1本目はコント」との方向性で6組が一致したのではないでしょうか。準々決勝、準決勝では1本目に漫才を披露する組が多かったので、「それまでの戦い方とは違うんだな」と個人的には興味深く感じました。
──視聴者らからは、たとえば次回以降「1本目は漫才、2本目はコント」という風に全組固定にした方がいいのではという意見も出ていますね。
これはあくまで個人的な考えですが、両方混ぜこぜで見たときのおもしろさが必ずあるので、視聴者のみなさんにはなんとかそのワクワクを一度共有していただきたいんです。
──分かります。私も大阪大会準々決勝を見に行きまして、26組・合計52本のネタを5時間半に渡って鑑賞したんです。漫才、コントが混ぜこぜで披露される『ダブルインパクト』の醍醐味を堪能し、多くの人にそのおもしろさを味わってほしいと思いました。

そうなんです、あのおもしろさを視聴者の方にもなんとか…と。決して思いつきで「おもしろいんです」と言っているわけではなく、実際に準々決勝、準決勝を見て、あらためて「これは一つの形としてすごいぞ」と。なによりこの大会は「芸人さん本人が選べる」ということを大事にしたい。それが『ダブルインパクト』という賞レースの誠実さだと思っています。もちろん、あくまですべて私個人の考えですから、関係者のみなさんとさらに良い大会にするために議論を重ねていきたいです。
──お笑いの賞レースが多数誕生していることによる、芸人、お笑いファン、両方の「賞レース疲れ」も懸念されています。しかし芸人としては「今年はこの大会に力を入れて、こちらは来年に」とローテーションや選択肢の幅が出てきて、それもおもしろいんじゃないかと。
みなさん、ネタの消費と戦って各賞レースに出場されていらっしゃると思います。すべて出場される方もいれば、たとえば「『ダブルインパクト』なら自分たちはやれるかもしれない」という方もいらっしゃるはず。『ダブルインパクト』はそうやって芸人さんたちが賞レースを「選ぶ」という要素の一つになった気もします。私たちとしては、賞レースをやるからには芸人さんのお役に立ちたいですし、そういう場所であり続けたいので。
■ 昨年は粗品の審査が話題に「覚悟をすごく感じました」
──中屋敷さんは大阪の若手芸人の登竜門『ytv漫才新人賞』の総合演出も担当されています。芸人のみなさんに話を訊くと「『ytv』は若手賞レースのなかでもっとも過酷だ」と。
まず「手見せ」と呼ばれる事前審査があって、それを通過した組だけが決定戦出場をかけた「ROUND」に出場できます。決定戦に出るまでの道のりが長いですし、「ROUND」も3回実施するので、勝つチャンスも高ければ負ける回数も多い。せっかく「ROUND」に進んでもそこで負けるとまた次の事前審査から挑戦しなければいけないので、それが過酷と言われる所以ではないでしょうか。

──若手芸人は口を揃えて「手見せの審査を通過するのが難しい」とおっしゃいますね。
手見せの審査員のみなさんも、もしそれが劇場で笑いに行っているものであれば、気楽に大笑いするはず。でも、細かいところを見逃したら、芸人のみなさんに対して申し訳が立たない。出場者をリスペクトしているからこそ、みなさん真剣に、そして厳しく審査をしていらっしゃると思います。
──審査員といえば2025年3月開催『第14回ytv漫才新人賞決定戦』で、賞レース初審査となった霜降り明星・粗品さんが話題になりました。
Tverでもこれまでの『ytv』の何倍もの再生数を記録し、ものすごい反響となりました。お笑いの賞レースの新しい1ページになったと思います。霜降り明星さんは2018年の『ytv』王者ですし、第14回大会は全出場者が芸歴的に粗品さんの後輩にあたり、なによりうちの賞レースは審査コメントもたっぷり時間をとってオンエアできるので、「粗品さんの審査がより輝ける場所ではないか」とオファーをさせていただきました。でも70点台の点数は『M-1』初期以外で見たことがなかったので、スタッフがざわつきました(笑)。
──視聴者もびっくりしたはず。
ただ、これはすべての審査員の方々に言えることですが、みなさんがそれぞれしっかりとした審査軸を持ち、真摯に、誠実に出場者のネタを見ているんだなって。ですので粗品さんの70点台にも、審査をする立場としての覚悟をすごく感じましたし、ハイヒールのリンゴさんと粗品さんの意見がぶつかり合ったところも一流同士だからこそ。ご自身の軸を持って審査してくださっていることが分かりました。また、そのために審査員が5人いて、その合計点数で勝者が決まるようになっているので。

──『ytv』は良い意味で毎回「本命不在」だと思います。特に近年、『ytv』をきっかけにほかの賞レースでも結果を残す若手が目立ちます。
たしかに3、4年目でまだ広く知られていない芸人さんたちが、上の芸歴の人たちをまくることが増えてきた印象があります。第13回優勝の空前メテオさんや、第13回・第14回で決定戦に進出したぐろうさんは、まさにそうですよね。私たちとしてもここ数年、そういったところに時代の変化を感じます。
──『ダブルインパクト』『ytv漫才新人賞』を制作されて、あらためて中屋敷さんはお笑いの賞レースに対してどのような意識で携わられているか教えてください。
「絶対に芸人さんたちの邪魔をしたくない」ということです。それを大前提として、新しいことやほかとは違う要素を考えたい。バラエティ番組ははみ出すおもしろさがありますが、賞レースはそうしないことが私のこだわりです。やっぱり賞レースは芸人さんたちが命がけでやっていらっしゃいますし、それと向き合う以上、バラエティとは異なるラインを引いて作っていかなければいけません。その点はこれからもブレずに携わっていきたいです。
◇
『漫才Lovers』は9月7日・16時より、『ytv漫才新人賞 ROUND1』は9月14日・16時より放送される(関西ローカル、TVerで見逃し配信あり)。
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
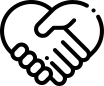 コラボPR
コラボPR
-

大河ドラマ『豊臣兄弟!』解説コラムまとめ【毎週更新】
2026.2.6 11:00 -

【大阪バレンタイン】梅田・心斎橋・難波・天王寺まとめ[2026最新]
2026.2.5 16:15 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫
2026.2.5 11:00 -

「奥大和」ってどこ…?奈良で絶景アウトドア4番勝負[PR]
2026.2.4 17:00 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.2.4 11:00 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】
2026.2.3 12:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.2.3 11:00 -

人気!大阪でリンツチョコレートのアフタヌーンティー[PR]
2026.2.2 12:00 -

絶景なのに【穴場】…梅田・飲食フロアを網羅[PR]
2026.2.2 07:00 -

疑ってごめん、宮崎。「何でも極上」は本当だった![PR]
2026.1.31 08:00 -

神戸で極上いちごスイーツの祭典…人気シェフ夢の共演[PR]
2026.1.29 17:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.1.26 13:00 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]
2026.1.23 10:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも
2026.1.21 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題
2026.1.19 11:30 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版
2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]
2026.1.14 11:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ
2025.12.30 12:00 -
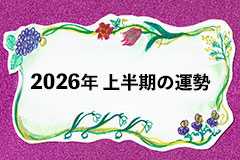
【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?
2025.12.26 00:00 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】
2025.12.20 19:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア






 人気記事ランキング
人気記事ランキング




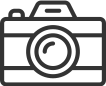 写真ランキング
写真ランキング












 ピックアップ
ピックアップ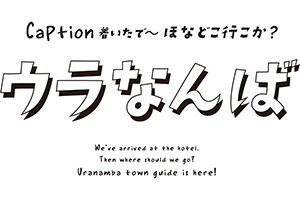

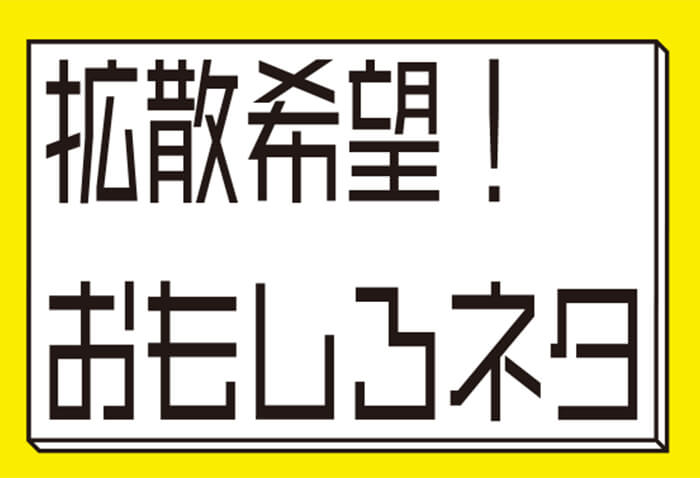


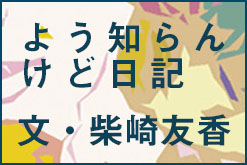

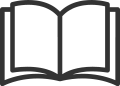 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本